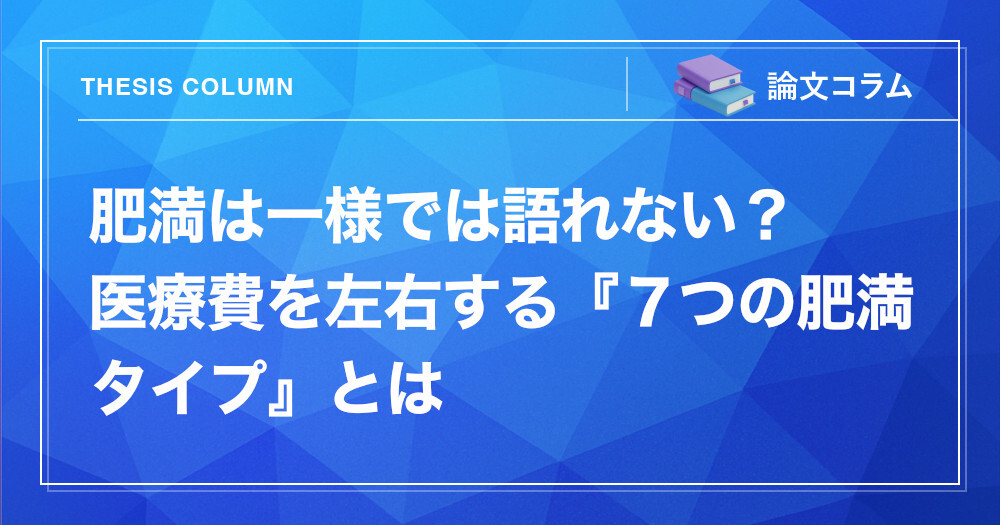医療費の増大が社会課題となっている日本において、生活習慣病の主なリスク因子の一つである「肥満」への予防・対策を検討している自治体は多いのではないでしょうか。実際、肥満は糖尿病や高血圧、脂質異常症といった合併症を引き起こし、医療費を押し上げる要因でもあります。
しかし、全ての肥満患者が同じ状態にあるわけではありません。今回ご紹介する研究*1では、肥満患者の実態や予後には様々なタイプがあり、一様には語れないことが明らかになりました。
論文名:Novel subgroups of obesity and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis
レセプトビッグデータのクラスター解析によって明らかになった高度肥満の様々なタイプと予後の関係
肥満を分類すると見えてくる個別介入の必要性
この研究の目的は、これまで「肥満」とひとくくりにされがちだった人々を、新しい「タイプ」に分類することです。
研究チームは、DeSCヘルスケアが提供する約344万人の医療データベースから、重度の肥満(BMI35以上)の患者9,494人を抽出し、過去の病気の診断名、処方された薬、受けた治療といった医療情報をもとに分析を行いました。
分析の結果、肥満は「高血圧・脂質異常症・糖尿病合併タイプ」や「未受診タイプ」などの7つに分類されました。特筆すべきは、病院への受診歴がほとんどない「未受診タイプ」が、死亡リスクが最も高かったことです。
この結果は、「肥満を単一の疾患として捉えるのではなく、それぞれの特徴に応じた肥満対策で介入する必要がある」ことを示しています。
データから見えてきた「7つの肥満タイプ」
この研究で特定されたタイプは以下の7つです。
タイプ1(21.1%):高血圧、脂質異常症、糖尿病を合併しているタイプ。最も人数の多いタイプです。
タイプ2(20.8%):糖尿病と網膜症を合併しているタイプ。透析導入リスクが高いことが明らかになっています。
タイプ3(16.0%):アレルギー疾患を合併し、比較的若く男性が多いタイプ。
タイプ4(11.9%):眼疾患とアレルギー疾患を合併しているタイプ。
タイプ5(10.8%):心血管疾患、糖尿病の合併、人工関節などの手術歴のあるタイプ。透析導入リスクが最も高く、死亡リスクが2番目に高いタイプでした。
タイプ6(10.2%):医療機関への受診歴がほとんどない「未受診タイプ」。7つのタイプの中で最も死亡リスクが高いことが明らかになりました。
タイプ7(9.2%):医療機関への受診はあるものの、合併症を示す医療情報がほとんどなく、死亡リスクも透析導入リスクも最も少ないタイプ。このタイプは「体質的には健康な肥満」と見なされます。
医療未受診グループの深刻な予後
特に注目すべきは、タイプ6「未受診タイプ」です。
ほとんど病院にかからないこのタイプは、死亡するリスクが健康な人と比べて約17倍と、全タイプの中で最も高くなっていました。この結果は、医療へのアクセスや継続的なフォローアップがないことが、肥満者の予後を極めて悪くする可能性を示唆しています。
一方で、死亡リスクも透析導入リスクも少ないのは、タイプ7「体質的には健康な肥満タイプ」です。定期的に医療機関を受診しているものの、過去の病名、処方された薬、受けた治療などの医療情報が少ないことから、「体質的には健康な肥満」と定義されます。
この発見は、BMIの数値だけでなく、合併症の有無や医療介入の状況を考慮した、より詳細な評価の重要性を強調しています。
研究の注意点(限界について)
なお、この研究結果を解釈する上での注意点として、主に2点が挙げられています。
一つは、今回の結果が日本人を対象としたもので、海外のすべての人に当てはまるとは限らないことです。もう一つは、「未受診」と「死亡リスクの高さ」の関連性を示したもので、それが直接的な原因だと証明したわけではない点です。
【保健観点】タイプ別の適切な介入を
この研究は、肥満という一つの診断名の中にも、多様なタイプと予後が存在することを明らかにしました。 肥満を単なる体重の問題として捉えるのではなく、その背景にある合併症や医療受診状況を複合的に評価することの重要性を示しています。
保険者にとって、レセプトや健診データを活用した個別のリスク評価は、被保険者の健康増進と医療費適正化の両立に向けた、強力な武器となるでしょう。
ハイリスクグループへの集中的な介入
未受診タイプ(タイプ6)や、心血管疾患や糖尿病を抱えるハイリスクなタイプ5に対しては、積極的に健康診断や保健指導を促すためのアプローチが必要です。
例えば、受診勧奨の強化や、重症化予防のための医療機関との連携を深めることで、将来的な医療費の削減につながる可能性があります。
データに基づいたターゲット選定
従来の一律的な保健事業ではなく、レセプトや健診データを用いた分析により、被保険者個々のリスクレベルを正確に把握することが可能になります。これにより、介入の必要性が高いハイリスクタイプに資源を集中させ、効率的で効果的な保健事業を展開することができます。
「健康な肥満」グループの発見
体質的には健康な肥満タイプ(タイプ7)は、現時点では合併症リスクが低いと評価されました。
このグループに対しては、過度な医療介入を避けつつ、健康状態の維持・悪化防止を目的とした、よりライトな介入(健康情報の提供など)が適切かもしれません。
※本研究には、保険者様の効果的かつ効率的な保健事業の実施に資する範囲で、アカデミアや製薬企業による論文発表などのエビデンス創出に活用することに利活用許諾をいただいた匿名加工情報、および提案募集制度を介して提供を受けた行政機関等匿名加工情報が用いられています。
引用
1.Takeshita, S, Nishioka, Y, Tamaki, Y. et al. Novel subgroups of obesity and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis. BMC Public Health 24, 124 (2024).
https://doi.org/10.1186/s12889-024-17648-1
監修医師:石原藤樹